障子紙を利用した手軽にできる蛍光灯カバー
今回は障子紙を利用した蛍光灯カバーの紹介をします。意外と簡単に制作できて、材料も100均で手に入るので手軽にできます。これをするだけで、ただの無機質な蛍光灯が光と模様による美しい造形物に様変わりします。今回は作業手順について簡単にまとめましたので、興味があれば是非やってみてください。
障子紙を適切な大きさに切って折り畳んで切り絵にする
障子紙は大体180cm × 90cm以上あるので、蛍光灯のサイズに合わせて切ることをおすすめします。切った障子紙は4等分や8等分に折り畳み、模様を切り抜けば、一気に切り絵が障子紙全体にできるので、割と短時間で切り抜き作業が完了します。
切り抜く模様に関しては何でも良いでしょうが、私は今回和柄を参考にして切り絵を作成しました。和柄はシンプルですがとても洗練されていて、デザインに利用しやすいのがメリットです。障子紙との相性も良く、とても上品な雰囲気の切り絵ができます。
計算して模様を配置すれば、畳んだ障子紙を開いた時に一定の模様にすることもできますが、少し違いを生み出して遊び感を出すのも良いと思います。
障子紙を重ねて模様を目立たせ光を柔らかくする
切り抜いた障子紙をそのまま蛍光灯に被せても良いですが、これでは蛍光灯の光が切り抜きの隙間から見えすぎてあまり格好が良くありません。光が強すぎると和柄もあまり目立たなくなってしまうのも難点です。
これを解決するのが障子紙を上からもう1枚重ねて蛍光灯をカバーする方法です。これによって和柄がよく見えて光も柔らかくしてくれます。障子紙の固定は剥がれにくい業務用のマスキングテープを利用しています。
このプロジェクターは元々は普通教室に配備されていたものです。昨年度65型のモニターが普通教室に全て配備されたため、プロジェクターが不要になって余っていたものを使っています。時々メディアアート系の動画を流したり、美しい画像を表示するなど、美的な刺激を生み出す仕掛けとして利用しています。
空間を装飾する魅力も美術教育の大切な視点
アートやデザインのある空間を生徒に日常的に体験してもらえるようにすることは、生徒の美意識に強く働きかけることができると考えています。もしも、こういった仕掛けがあまりにも行動で難しいものであれば、生徒にとって自分事として考えることが難しいかもしれません。しかし、この蛍光灯カバーの作成は難易度的にはそれほど高いことではなく、私が担当した生徒は和柄をステンシルで作成したことさえあるので、心理的なハードルもそれほど高いものにはならないと思います。やればできるという感覚があれば、それをいつか発揮することもできるでしょう。
お金を出せば良い照明を購入することができますし、デザイン性溢れる空間も購入することもできます。しかし、ちょっとした工夫でも魅力的なものが創れるという自信があれば、自由にアレンジを楽しみ、自分らしい空間づくりが可能になります。
そういったことにつながる美意識を培うきっかけづくりとして、刺激的な空間づくりを美術室で実践し続けることが大切であると私は考え、できることから取り組んでいます。工夫のヒントになるものは日常生活や美術館(もちろん美術の教科書や資料集なども)、インテリアショップ、雑貨屋など様々なところに潜んでいます。日頃から鑑賞マインドを発揮していれば、自然とやりたいことは見つかり、やりたいことリストが膨大な状態になっていきます。
このようにしていると、時間はいくらあっても足りないものですが、自分自身の直感を信じて優先したいことを決めて行動に移していれば、自然と成果が出るものです。なので、これからもモチベーションのままに夢中で創造活動に取り組んでいきたいと思います。
最後まで読んでくださってありがとうございました。今回は障子紙を利用した蛍光灯カバーについて紹介しました。簡単にできて、造形的にも大変美しいものになるので、おすすめのDIYです。できそうなところがありましたら、是非やってみてください!
それではまた!

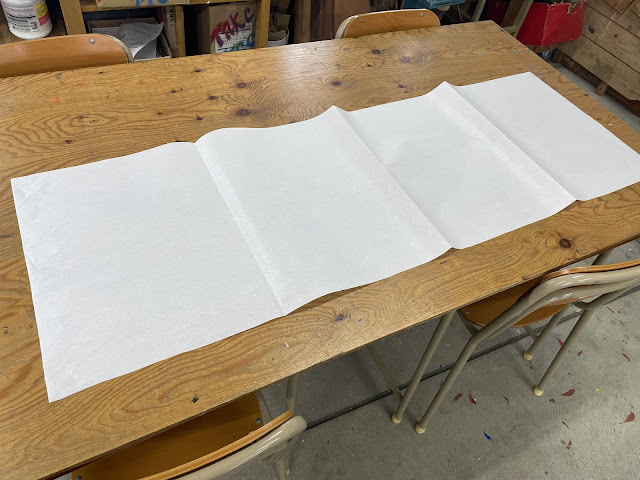









コメント
コメントを投稿